
システム開発の相場を徹底解説|単価から費用管理・外注のポイントまで
システム開発の費用相場と単価の基礎知識

システム開発を外注する際、最も気になるのが費用の相場や内訳です。費用が不透明だと予算オーバーのリスクや開発の進行トラブルも招きやすくなります。本記事では、システム開発にかかる単価の概要やシステム開発費の構成、費用相場の実態から抑えるコツ、そして外注先選びのポイントまで詳しく解説。費用管理に不安がある方や予算計画の見直しを検討中の方の参考になる内容です。
目次
1.システム開発の単価とは何か理解しよう
– 単価の計算方法と主要要素
– 単価に影響する技術力と経験
2.システム開発費は何で構成されているか
– 人件費の割合と計算根拠
– 要件定義から保守まで費用分布
3.システム開発費用相場の具体的な基準
– システム規模別の費用目安
– 開発工程ごとの費用傾向
– 費用相場の変動要因と注意点
4.費用を抑えるシステム開発の工夫と対策
– 機能の優先順位でコスト最適化
– オフショア開発の活用メリット
– 内製化と外注のバランスづくり
5.失敗しない外注先選びのポイント
– 実績と技術力の確認方法
– コミュニケーション重視の選定基準
– 複数社比較と見積もり依頼の進め方
まとめ:システム開発の費用相場を理解して失敗しない外注を実現するために
◆システム開発の単価とは何か理解しよう
システム開発の単価とは、エンジニア1人が1ヶ月間にかかる費用を指すことが多いです。これは「人月単価」と呼ばれ、技術者の役割やスキル、経験年数によって大きく異なります。一般的にプログラマーの単価は40万〜60万円程度、SE(システムエンジニア)が60万〜100万円程度が目安です。この単価に人数や期間を掛け合わせて、開発全体の人件費が算出されます。理解すべきは、単価はあくまでも費用全体を構成する要素の一つであり、複数の技術者がどれだけ関わり、どのくらいの期間が必要かによって総額が変わってくるという点です。
単価の計算方法と主要要素
単価の計算は比較的シンプルで、「人月単価 × 必要人数 × 開発期間(月数)」で求められます。例えば、単価80万円のシステムエンジニア3人が3ヶ月作業すれば、80万円 × 3人 × 3ヶ月=720万円となります。また、単価を決める大きな要素はスキルセットと役割です。プログラマーは比較的単価が低く設定され、複雑な設計やプロジェクトマネジメント、システムアーキテクトのような高度な専門職は単価が高めに設定されています。
さらに、単価は地域や発注形態によっても異なります。国内主要都市の技術者単価と地方、さらにはオフショア開発先の海外技術者単価は大きく異なります。また、案件の難易度が高いほど単価設定も高額になりやすい傾向にあります。この単価計算で注意したいのは単純に人数×期間だけで済まないことです。専門性や緊急対応、設計の複雑さによって変動があります。ゆえに、単漠とした相場ではなく、自社プロジェクトの要件に合わせて、動的に見積もりを検討することが不可欠です。
単価計算の例
| 職種 | 単価(人月) | 人数 | 期間(月) | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|
| システムエンジニア | 80万円 | 3人 | 3ヶ月 | 720万円 |
| プログラマー | 50万円 | 2人 | 3ヶ月 | 300万円 |
役割ごとの単価目安
单価に影響する技術力と経験
技術力と経験は単価の決定において非常に重要な要素です。経験豊富で高い技術力を持つエンジニアは、プロジェクトに柔軟に対応できるだけでなく、問題発生時にも迅速に対処ができるため高単価になりがちです。たとえば、AI活用やブロックチェーンのような先進技術分野の開発では、高度なスキルを持つ専門技術者の単価が跳ね上がります。逆に、使用技術が標準的で比較的簡易なWebサイト開発等の場合は、単価も抑えめとなるケースが多いです。
また、技術力と経験は単純なスキルレベルだけでなく、過去の実績や業界特化度合いも影響します。たとえば、医療分野や金融、ECサイトの構築での実績が豊富な技術者は、ドメイン知識も備えているため付加価値が高まり、その分、単価も割高になります。一般的にプロジェクトマネージャーやプリジェクトリーダーが持つ経験の豊富さも単価に反映されることが多く、多数のメンバーの進行管理やトラブル解決能力は価格に込められるということになります。
さらに、技術のアップデートは日進月歩です。最新技術に対応できる人材ほど貴重となり、その希少価値が単価を押し上げています。こうした事情は人材市場にも現れており、通常に比べて需要が多い先端スキルのエンジニアは各社で争奪戦の状態となっています。CS技術だけでなく、海外の多国籍チームと連携する語学力やコミュニケーション力も、単価に影響します。単価設定を理解するときは、「技術力×経験+専門分野+コミュニケーション能力」という掛け合わせが影響することを意識することが重要でしょう。
◆システム開発費は何で構成されているか
システム開発費用は大きく分けて「人件費」と「諸費用」の二つに分類できます。人件費が全体の80%近くを占めることが多く、開発に関わる技術者の時間や能力が費用に直結します。一方、諸費用には開発環境費やサーバ、ソフトウェアのライセンス費用、さらには通信費やオフィス賃料などが含まれます。この構成を理解することが、正確に費用感を把握しやすくなる第一歩です。
人件費の割合と計算根拠
人件費は、プログラマー、システムエンジニア、プロジェクトマネージャーなど、開発に関わるあらゆる技術者の「人月単価」に開発期間や人数を掛け戻して計算されます。一般に費用の70-80%程度を人件費が占めるのは、膨大な工数と専門技術が要求されるためです。たとえば、新規機能の設計や開発、テストとリリースまで、多くの作業をエンジニアが担当することで工数は膨大に膨れ上がります。算出根拠は、開発会社の人材層別単価情報や今までの実績データ、実施工程の難易度等です。その人員構成と経験値のバランスも費用を適切に見積もるキーとなっています。
要件定義から保守まで費用分布
システム開発費用は工程ごとに分布しており、それぞれにかかるコストの偏りが見られます。一般的には「要件定義」がプロジェクト全体の5~25%程度、「設計」が20~30%、実際の「プログラミング(実装)」が全費用の30~50%ともっとも大きなウェイトを占めます。そして、「テスト」や「デプロイメント(リリース作業)」などに15~25%程度が配分されます。
さらに、リリース後の「保守・運用」も見逃せず、運用継続費用として毎年一定割合のコストが発生します。一般的には、システム開発費用の年額12~15%が相場といわれています。大手のシステム開発ベンダーの場合、年額20%を保守料として算出していることもあります。保守継続費用は人件費が大部分ですが、ここには運用時間外対応など緊急対応も含まれるケースがあり、「人月単価」が保守段階1でも徐々に積算されていくのが現状です。
要件定義の品質がプロジェクトの費用面に大きな影響を与えるため、時間やコストをかけつつしっかり設計し、仕様のブレを減らすことが結果的に無駄な追加開発を防ぐ近道です。
◆システム開発費用相場の具体的な基準

システム開発の費用は、規模や開発内容、利用する技術次第で大きく差が出ます。ここではおおまかな相場や開発工程ごとの傾向、注意すべきポイントを見ていきましょう。
システム規模別の費用目安
単純にシステムの規模により費用相場は変動します。小規模なコーポレートサイトやランディングページ開発は数十万円から、ECサイトや予約管理システムなど中規模の開発だと500万円程度が一般的です。また、マッチングプラットフォームやSNSのような大規模かつ多機能システムになると、1,000万円以上かかる場合も珍しくありません。業務の種類や機能のカスタマイズ度合いにより大きな差があります。
加えて、要望に応じた対応OS数(スマ-トフォン・PCなど)や特定の技術(AI、リアルタイム連携など)を用いると、費用帯は跳ね上がる傾向があります。まさに「規模×機能×技術」でコストが変わるということです。したがって、単に想定金額を知るだけではなく、自社ニーズに合わせた詳細見積りが重要です。
開発工程ごとの費用傾向
前述の通り、要件定義、設計、プログラミング、テスト、デプロイ、リリースと段階を追うごとにコストが偏ります。設計と実装で費用の7割以上が掛かり、慎重な仕様設計を欠かしてしまうと手戻りが発生して試験や修正工程の費用が膨らむことに直結します。開発テストフェーズには自動化ツール導入で費用削減も試みられていますが、それでも作業量は多岐にわたります。
また、「ウォーターフォールモデル」が基本の国内開発では、後工程で仕様変動が起こると大幅工数増になるため、依頼前の要件固めがとても重要です。その反面、アジャイル開発では成果物を揉みながら費用配分の柔軟性も持たされており、利用スタイルによって費用分布が変わることを覚えておきましょう。
費用相場の変動要因と注意点
費用相場は、大きく下記の3つで揺れが生じます。まず「技術的複雑度」。AIや音声認識のような先端要素は単価も工数もかかるため、予算は膨らみやすいです。次に「要件の確定度と開発期間」。中途半端な要件で発注すると、途中で仕様変更が頻発してしまい、結果的に相場以上のコストが発生します。最後に「外注形態」。オフショア活用でコストを削減できることもありますが、コミュニケーションコストや品質管理の難しさがリスクになります。
したがって単価と規模の単純な掛け算だけではなく、変動要因をマネジメントしていくこともサービス選定で失敗しない秘訣です。
◆費用を抑えるシステム開発の工夫と対策
システム開発の費用は工夫次第で大幅に抑えられます。最も効果的なのは、予め重要な要素を選んで優先順位をつけて進め、効率の良い予算配分を行うことです。一方、コスト差の大きい外注方法や内製化の選択もポイントになります。
機能の優先順位でコスト最適化
開発に入る前に、どの機能が事業に必要不可欠かを明確にし、優先順位を付けて取り組むことが大切です。すべての機能を盛り込もうとすると、それだけで費用が高騰します。最低限必要なコア機能に絞り、まずはその部分の開発を目指すことで納期の短縮やコスト抑制が期待できます。たとえば、販売管理システムであれば、注文管理を最優先とする代わりに、細かな統計機能は後回しにするといったように検討をすすめます。機能をすべて盛り込んだことで、現場で使い切れない機能まで増えてしまったというケースは意外に多く発生するため、そういった理由からもシステム開発は最低限必要な機能から優先順位をつけて進めて行く方がよいでしょう。
また、システムユーザーからの要望や実際の業務フローを十分ヒアリングし、無駄な仕様を排除することも忘れてはいけません。途中で新しい要望が加わるたびに開発工数も急増するため、機能追加は段階的に行うプランニングが賢明です。このようなローリングリリース型の考え方は費用対効果の高い投資を可能とします。
オフショア開発の活用メリット
人件費が高騰している日本においては、オフショア開発を活用するメリットも大きいです。ベトナムやマレーシアなど新興国のIT人材は増加しつつあり、日本と同等の技術力を安価で提供してもらえる場合があります。費用は国内の半分以下になることも珍しくありません。ただし、コミュニケーション面のハードルや納期管理、品質保証に注意が必要です。日本に拠点を持つオフショア企業を利用すれば、日本語でのやり取りが円滑で文化も近く、リスクを抑えつつコスト削減を図ることができます。加えて円安などの為替変動にも気をつけながら選択を進めると良いでしょう。
将来の仕様変更や保守運用面でのサポートもしっかり確認することが、安心感を持って費用削減の有効手段とするポイントです。
内製化と外注のバランスづくり
すべてを外注に依頼すれば、予算が膨らみがちです。そこで、一部作業を自社内で対応できる場合は積極的に内製化を検討してもよいかもしれません。例えば、要件定義やテストの一部、運用保守の一端を社内でまかなうだけでも、外注費用は確実に抑えることができます。
内製化は社内の技術レベルやリソースの把握が不可欠ですが、関係者の業務理解も深まるため、将来的なトラブルや改修コストの削減にも効果的です。反面、自社だけでは人手やノウハウが不足しがちな領域は外注するハイブリッド戦略が望ましいでしょう。
このバランスを模索することが、合理的な予算配分とプロジェクトの成功につながるのです。
◆失敗しない外注先選びのポイント
外注先は単に価格だけで選ぶと後悔しやすいので、実績・対応力・コミュニケーションの3点から慎重に選定しましょう。失敗しない発注へ向けたポイントを解説します。
実績と技術力の確認方法
まず開発会社の過去実績は信頼のバロメーターです。同じ業界や類似した開発内容での成功例があるかを確認しましょう。事例公開や顧客の声をチェックするほか、可能であれば直接問い合わせて技術者のスキルも目視できる体制かどうかを重視したいところです。
また高い技術力を持っているかは、エンジニアの実務経験や資格、最新技術への取り組み具合からも判断可能です。しっかりとした人材育成制度がある専門企業は長期的なパートナーとして安心できます。逆に単に低価格を謳う企業は、価格相応の成果にとどまるリスクもあるため、価格だけで判断せず実績を照合して検討することが鍵となります。
コミュニケーション重視の選定基準
システム開発は要件の正確な伝達が重要なため、担当者やチームとのコミュニケーションが円滑にできるかは重要なポイントです。レスポンスの早さ、問い合わせ時の対応説明の理解度、定期ミーティングの実施状況などをチェックしましょう。
日本語対応はもちろん、遠隔地との連携も増えているため、オンラインツールの活用がスムーズに対応できるかどうかも確認しておく必要があります。文化や報告の形式、一方的にならず相談しやすい環境があるかどうかも、事前に把握しておくと良いでしょう。コミュニケーション不足はトラブルの温床なので、不安そうなサインがあったら候補から除外するほうが安全です。
複数社比較と見積もり依頼の進め方
システム開発の場合は特に1社の見積のみでは、価格の妥当性が判断できません。最低でも2〜3社から見積もりを取得し、技術方向性、費用明細、リスク管理の姿勢を比較すべきです。見積もり依頼時は「同一条件をできるだけ詳細に伝える」ことが公平な価格競争を促します。
比較するうえで、価格だけでなく提供される付加価値や納期、フォロー体制なども総合評価し、刻々と現場で変わる状況にも適応可能か対話を通じて見極めることが理想です。最終段階では比較結果をもって候補先と交渉し、条件のブラッシュアップを行うことができれば、最善の発注先へとたどり着くことができるでしょう。
◆まとめ:システム開発の費用相場を理解して失敗しない外注を実現するために
システム開発の費用相場は技術者の単価やプロジェクト規模、採用する技術力、開発工程によって大きく異なります。人件費が全体の中心であり、単価計算の理解は予算策定の出発点です。工程ごとの費用配分やシステムの目的に合わせた必要機能の選定は、コスト効率化に欠かせません。また、オフショア開発の活用によるコストダウン、内製化とのバランス検討も賢い選択肢となります。
外注先の選定では、単価だけでなく実績や技術力、そして何より相互のコミュニケーションのしやすさを重視しましょう。複数社から見積もりを取り、プロジェクトのニーズを共有したうえで比較検討することで、納得感のある発注が可能になります。
はじめに費用構造をしっかり理解し、信頼できるパートナーと事業の成長につながるシステム開発を進めることができれば、予算管理もスムーズになり、無駄なコストやトラブルを避けられるはずです。今後は具体的な見積もり依頼やーマッチングサービス利用を視野に、自社に合った最適なシステム開発の投資判断をぜひ実践していきましょう。
◆基幹システム開発・導入支援はエイ・エヌ・エスへ

株式会社エイ・エヌ・エスは、オーダーメイドの基幹システム開発を主軸に、創業35年以上にわたり多様な業界・業種のシステム開発に携わってきました。
スクラッチ開発による柔軟なカスタマイズ対応に加え、既存システムの再構築や運用支援、保守引継ぎサービスなど、上流から下流まで一貫した体制で企業のIT基盤を支えています。
- IT-Trust:オーダーメイドのシステム導入で企業のDX推進を支援
https://www.ans-net.co.jp/ - システム再構築サービス:業務時間を削減し、生産性向上を実現
https://www.ans-net.co.jp/lp/rebuilding/ - 保守引継ぎサービス:最短1ヵ月で“任せられる”保守体制へ
https://www.ans-net.co.jp/lp/maintenance/ - IT相談サービス:システム・IT課題を無料で相談可能
https://www.ans-net.co.jp/it-advice/ - 内製化支援サービス:社内開発体制の立ち上げを支援し、持続的なDXを実現
https://www.ans-net.co.jp/lp/insourcing/
エイ・エヌ・エスは、上流工程の確実な支援を通じて、企業のIT資産を未来へつなぐパートナーとして伴走いたします。
検討段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。
「システム開発の相場を徹底解説|単価から費用管理・外注のポイントまで」に関連する記事

2026.01.15
システム開発における基本設計とは?進め方から成果物まで解説
システム開発の基本設計は、要件定義から詳細設計へと進む重要な工程です。本記事では、初心者から中級者向けに基本設計の役割や進め方、特徴的な設計書の種類や作成のポイントをわかりやすく解説します。 […]
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発
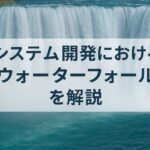
2025.12.23
システム開発におけるウォーターフォールを解説:工程ごとの特徴と他手法との比較も
ウォーターフォール開発は、システム開発の中でも伝統的で多くの大型プロジェクトに採用されてきた手法です。本記事では、ウォーターフォールの各工程を詳しく解説し、アジャイルなど他の開発手法との違いもわかりやすく紹 […]
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.12.11
システム開発トラブルの原因と事例徹底解説!失敗回避と法的対応のポイント
システム開発におけるトラブルは、遅延や予算超過、仕様の齟齬、さらには運用段階での障害など多岐にわたります。本記事では、トラブル発生の原因から具体的な事例までをわかりやすく紹介するとともに、発注者や開発者が取 […]
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.12.02
システム開発を依頼するなら押さえたい!依頼書作成から費用・流れを解説
システム開発を外部に依頼する際、適切な準備と知識がなければコストや納期、品質で失敗するリスクが高まります。本記事では、依頼書の作成から全体の進行フロー、費用相場、開発手法の選び方、そして発注先の探し方まで、 […]
- #IT化推進
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.10.17
システム開発におけるV字モデルとは?概要やメリット、他のモデルについても解説
システム開発にはさまざまな工程や手法があり、その中でもV字モデルは多くの現場で活用されています。 効率的かつ品質の高い開発を目指す方にとって、どのような開発モデルを選ぶかは重要なポイントです。 […]
- #IT関連情報
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.08.25
【2025年最新版】システム開発には補助金・助成金の活用を!
業務効率化や顧客満足度向上がカギとなっている今「新しくシステムを導入したい」「今のシステムを刷新してより生産性の向上に努めたい」という企業が多くなっています。しかしながら、システムの開発や再構築には多額の費用がかかるため […]
- #システム再構築
- #助成金・補助金
- #基幹システム・Webシステム開発
- #生産性向上

2025.06.25
レガシーシステムはなぜなくならない?使い続けるリスクを解説
DXの最大の障害とされるのがレガシーシステムです。 企業がITシステムの導入に取り掛かったのは、今に始まったことではなく、中には1980年代ごろから導入しているケースもあります。そのような中で、最先端を進ん […]
- #DX(デジタルトランスフォーメーション)
- #IT化推進
- #システム再構築
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.05.21
突然の“保守打ち切り”がもたらすリスクと、備えるべき選択肢
近年、開発会社の倒産やエンジニアの流出により、システムの保守が継続できなくなるケースが相次いでいます。 特に、企業の業務を支える基幹システムが「孤児化」する事態は、業務継続に深刻な影響を及ぼします。 本コラムでは、システ […]
- #システム保守
- #基幹システム・Webシステム開発
- #業務効率化
- #生産性向上

2025.04.25
システム開発の要件定義、発注側がすべきこととは?
システム開発は開発会社にすべて任せればいい、というわけではありません。経験が豊富なプロであっても発注側の意見や要望がなければ良いシステムを作ることは難しいでしょう。そこで大切となってくるのが「要件定義」です。要件定義では […]
- #システム保守
- #システム再構築
- #システム開発工程
2025.02.25
業務効率化にはシステム導入が鍵!最適な業務システム選定のポイントとは?
近年、日本企業が直面している大きな課題の一つに「人手不足」があります。少子高齢化の進行に伴い、労働力の確保がますます難しくなることが予想される中、企業にとって最優先で取り組むべき課題は「業務効率化」です。効 […]
- #IT化推進
- #UIUXデザイン
- #基幹システム・Webシステム開発
- #業務効率化



