
システム開発の見積もりを解説!見積作成のコツも紹介

システム開発の見積りについて、そもそも希望のシステムを開発してもらうのにどのくらいの作業と費用が適正なものなのか、判断することは難しいのではないでしょうか。開発したいシステムの規模が大きいのか、小さいのかということからしても、情報システム部やIT関連の知見がないと特に、想像しにくいかもしれません。
システムの見積りを行う際は、必要な機能や作業内容を洗い出し、工数化することになります。とはいえ、要望や概要が細部まで決まっていない段階であることも多く、その場合、見積り時点で分かっている情報から推測して見積もることになります。決まっていない部分が大きい程、着手後に見積り時点では見えなかった要件がでてくるため、工数のブレが生じることは避けられません。このブレを100%解消することは難しいにせよ、見積りの段階で要件が具体的に定まっていることが重要となります。
本コラムでは、見積方法や手法とあわせて、より精度の高い見積を作成するためにはどうしたら良いのかを解説していこうと思います。
◆見積りの方法と手法
システム開発の見積を算出する際には、決められたやり方に沿って行うことでより精度の高い見積を作成することができます。代表的な4つの方法をご紹介します。
①類推法
過去に開発したシステムの実績をもとに、今回の案件の費用や工数を見積もる方法を「類推法」といいます。内容や規模、機能などが似ているプロジェクトを参考にすることで、短時間でおおまかな見積りを出せるのが特長です。経験やデータを活かせるため、初期段階の概算見積りや社内検討時に向いています。ただし、過去の類似事例がない場合は使えない手法である点はデメリットといえます。また類似事例がある場合も、参考とする案件との違いを十分に考慮しないと、実際のコストや工数にずれが生じる可能性があるため注意しましょう。精度を高めるためには、比較対象を慎重に選び、条件の差を補正することが大切です。見積りのスピードと現実性を両立しやすい、実務で活用される手法のひとつといえます。
②パラメトリック法
「パラメトリック法」は、開発規模や機能数などの定量的な要素をもとに見積りを行う手法です。過去の実績データから、「画面1枚あたりの開発工数」や「機能1つあたりのコスト」といった平均値(パラメータ)を導き出し、それを今回の案件に当てはめて算出します。根拠が数値に基づくため、客観性が高く、一定の精度を保ちながら短時間で見積りを出せるので納得感が得やすいのが特長です。一方で、パラメータが古い場合や、案件の特性が平均値と大きく異なる場合は誤差が生じやすくなります。また、デザインやUIの工数が反映されないというデメリットもあります。信頼できるデータをもとに活用することで、合理的かつ再現性のある見積りを行える方法といえます。
③プライスツーウィン法
「プライスツーウィン法」は、競合他社や市場の相場感をもとに、受注を獲得できる“勝てる価格”から逆算して見積りを行う手法です。技術的な工数計算よりも、顧客の予算感や競争状況を重視するのが特徴で、入札やコンペ形式の案件でよく用いられます。市場ニーズに即した予算に合わせた見積りができる反面、コスト構造を軽視しすぎると採算が取れなくなるリスクもあります。また、予算ベースのため、機能不足やフェーズ分けした開発になる可能性が大きいこともデメリットとして挙げられます。そのため、社内の実現可能な最低ラインと照らし合わせながら価格を設定することが大切です。ビジネス戦略の一環として活用される、営業的な側面の強い見積り手法です。
④ボトムアップ法
「ボトムアップ法」は、システム開発の各作業単位ごとに必要な工数やコストを積み上げて、全体の見積りを算出する手法です。設計、開発、テストなどの工程ごとに細かく見積もるため、精度が高く、条件や仕様の変更にも柔軟に対応できます。一方で、初期段階では情報が不十分な場合が多く、見積り作成に時間と手間がかかるのがデメリットになります。そのため、詳細設計や要件が固まった段階で用いることが一般的です。各作業の積み上げに基づくため、根拠が明確で社内共有もしやすく、精緻な予算管理や進捗管理にも向いた実務的な手法といえます。
4つの見積方法をご紹介しましたが、システムの種類や要件、見積りをする開発会社によって、適正な見積り方法が変わってきます。開発業者がより適切な見積手法を採用するためには、発注側で具体的な要件がどの程度固まっているかがカギとなります。
見積の基本的な内訳としては以下のような内容が挙げられます。
・要件定義費用
・設計費用
・開発費用
・デザイン費用
・導入費用
・検収/テスト費用
・保守費用
・購入費用
・交通費用
これだけの見積項目がある中で、何か一つ要件が欠けただけでも見積金額は変わってきてしまいます。こういった費用を正しく算出するためにも、見積りを依頼する前に、事前に要件、情報、データをまとめることが大切です。
◆見積もり前に確かめること
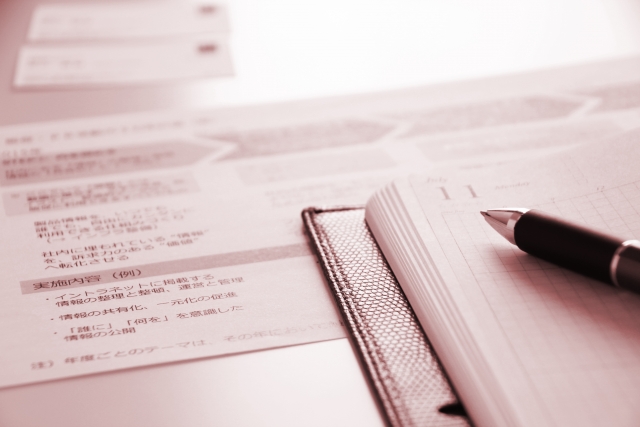
より精度の高い見積りを行うためには、具体的に要件が決まっていることが大切です。要件が固まっていないと、想定して見積もる部分や対象範囲外の項目がどうしても増えてしまいます。下記4つの項目をチェックしてから見積前に開発業者にヒアリングを依頼しましょう。
☑開発範囲・要件は明確ですか?
見積りの精度は、開発範囲や要件がどれだけ具体的に決まっているかで大きく左右されます。「どこまで作るか」「どの機能が必要か」が曖昧だと、開発側は安全側に見積りを膨らませるため、結果としてコストが高くなりやすくなります。最初に必要な機能や画面、対象業務を整理しておくことで、適切な見積りを得やすくなります。
☑前提条件は明確ですか?
システム開発では、利用する環境や外部連携、既存データの扱いなど、前提条件が見積りに影響します。これらがあいまいだと、後から追加作業が発生し、予算や納期にずれが生じやすくなります。開発を依頼する前に、前提となるOSやブラウザ、API連携の有無などを整理しておくことが重要です。
☑予算、期日はありますか?
見積りを作成する際には、予算や納期の目安を伝えることが大切です。限られた予算や決まった納期の中で優先すべき機能や開発方法を判断できるため、現実的な提案を受けやすくなります。逆に予算や期日を示さないと、開発側は安全策として高めの見積りを提示することが多くなります。
☑リスクや優先条件は考慮していますか?
開発には仕様変更や外部要因などのリスクがつきものです。また、全ての機能を同時に実現するより、優先順位をつけて段階的に進める方が効率的な場合もあります。見積り前にリスクや優先条件を整理しておくことで、開発側は現実的な工数やコストを計算しやすくなり、無理のないスケジュール提案につながります。
◆見積もりを作る際のコツ
実際、精度の高い見積作成に重要なこととして下記の3点がカギとなります。
①ヒアリングを実施して提案依頼書を作成する
システム開発を検討する際、「どこまで要件をまとめておけば良いのか分からない」「専門的な部分は相談しながら決めたい」と感じる方は多いでしょう。そのような場合は、見積もりを依頼する前に、まずヒアリングを実施してもらうのがおすすめです。打ち合わせの中で、提示できる情報をもとに開発範囲や目的をすり合わせ、予算・期日・優先事項を明確にしていきます。予算が限られている場合には、その中で実現できる内容を検討でき、納期が優先であればスケジュール上の制約も把握できます。
そして、ヒアリングを効率的に進めるためには、「提案依頼書(RFP)」を作成しておくことがポイントとなります。提案依頼書を作成することで、依頼側と開発側の認識が一致しやすくなり、見積りの精度も上がります。特に「必須の機能」と「あると望ましい機能」を分けて記載することが重要です。開発の優先順位が整理され、費用対効果や納期の検討がスムーズになります。万が一提案依頼書の作成が難しい場合は「現状の課題」や「実現したいこと」をまとめておくだけで、的確なヒアリングや見積もりにつながります。
②工数をもとに計算する
システム開発の見積りは、一般的に「工数」を基準に算出されます。工数とは、開発に必要な「作業時間」に近い概念で、IT業界では最も大きなコスト要素である人件費を算出するための指標です。代表的な単位には「人月(にんげつ)」と「人日(にんにち)」があります。
・1人月:1人が1ヶ月間で完了する作業量
・1人日:1人が1日で完了する作業量
たとえば、1名が3ヶ月、または3名が1ヶ月で作業を行う場合は「3人月」の工数と考えます。
システム開発は通常、【要件定義 → 設計(基本・詳細) → 開発 → 検収】という流れで進みます。見積段階で提示される費用は、これら工程のうち「設計」「開発」「検収」にかかる概算金額であることが多く、要件が固まっていない段階では誤差が生じることもあります。要件定義を通して「やること」と「やらないこと」を明確にし、開発範囲と機能数を確定させることで、初めて正確な見積りが算出されます。
見積では、期間・人数・担当者の役職・機能の難易度などを考慮して金額を計算します。たとえば、プロジェクトマネージャー1名(人月単価100万円)とプログラマー2名(人月単価70万円)が3ヶ月作業した場合、
(100万円×1名+70万円×2名)×3ヶ月=720万円
という計算になります。
このように、システムの規模や機能の複雑さによって必要な工数が変わるため、費用にも大きな差が生じます。見積りを依頼する際は、想定できる範囲で機能や要件を整理しておくと、現実的で根拠のある見積りを得やすくなります。
③要件を明確に定めておく
大まかな必要情報として、システムの“規模感”というものがあります。どのくらいの規模感のシステムなのか、と言われても大体などの想定はしにくく回答に窮すると思います。
管理したい業務(例:顧客管理、売上管理、在庫管理、勤怠管理等)、それに対し必要な画面数や機能数を想定することで規模感をはかることができます。例えば、営業管理ができるシステムを開発したいとしましょう。営業管理とは、営業担当者の行動予定のみ管理できれば良いのか、行動予定、顧客データの管理、見積・発注・納品までの書類作成・出力等、営業担当者のすべての業務を網羅することが理想なのか等によって、開発する範囲の大きさが想像できると思います。また、PCのみで利用することを前提にしたシステムか、スマートフォンやタブレット端末での利用を想定しているのかなどでも、規模の大きさが変わってきます。
システムの範囲が定まっていないと、規模をはかることは難しくなります。そのように考えると、要件を明確にすることで正確な見積りができる、という根拠がわかりやすいかもしれません。
◆システム開発の見積もりに差が出る理由
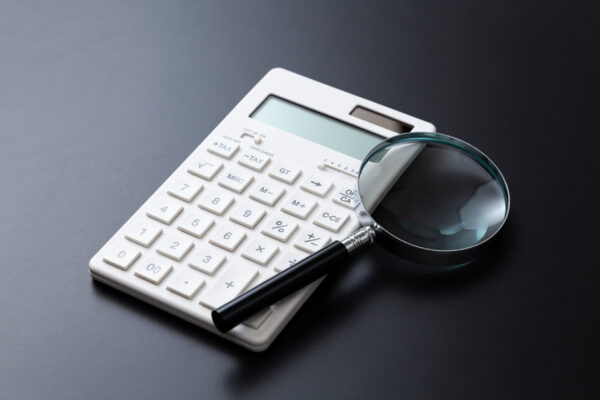
システム開発を検討する上で、複数のシステム会社に見積りを提出してもらうと、各社で金額が大きく異なるということがあります。金額が異なることに驚くと同時に、適正な価格かが分からないため判断がしにくい、ということになるのも珍しくないかもしれません。
仮に、詳細な要件を正確に伝えていた場合でも、人員やリスクの兼ね合いから余裕を持って金額を算出しているケースや、見積りの中に含まれる機能が最低限の機能数なのか、それとも要望を全て満たすことを想定して算出しているか、によっても金額が異なるものです。
発注者側が、納期、予算、システム規模、メンテナンス体制等を明確にすることで、ある程度同じ条件の見積りを得ることができます。まずは方向性を定めておくことが前提といえるでしょう。
システム開発に限りませんが、追加要望や別の依頼が出れば、それに合わせて費用は上がります。最低限で開発した場合を想定した予算であれば、別途、追加や要望が出た際に発生したら費用が発生することを念頭において検討をすすめるべきでしょう。
◆まとめ:システム開発の見積もりは慎重に
システム開発の見積もりは、単に金額を出す作業ではなく、要件や開発範囲、優先度、リスクを整理したうえで慎重に行うことが重要です。見積り手法には類推法やパラメトリック法、プライスツーウィン法、ボトムアップ法などがありますが、どの方法を選ぶかは案件の規模や情報の精度によって変わります。特に工数ベースでの算出は、人件費や作業量を明確にするため、後からのコスト誤差を抑える効果があります。依頼前にヒアリングや提案依頼書で要件を整理することで、開発側と認識を一致させ、より現実的で納得感のある見積もりにつなげることができるでしょう。
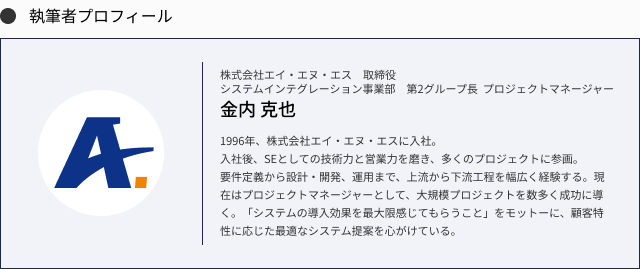
「システム開発の見積もりを解説!見積作成のコツも紹介」に関連する記事

2026.01.15
システム開発における基本設計とは?進め方から成果物まで解説
システム開発の基本設計は、要件定義から詳細設計へと進む重要な工程です。本記事では、初心者から中級者向けに基本設計の役割や進め方、特徴的な設計書の種類や作成のポイントをわかりやすく解説します。 […]
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発
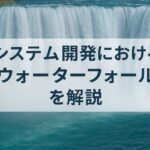
2025.12.23
システム開発におけるウォーターフォールを解説:工程ごとの特徴と他手法との比較も
ウォーターフォール開発は、システム開発の中でも伝統的で多くの大型プロジェクトに採用されてきた手法です。本記事では、ウォーターフォールの各工程を詳しく解説し、アジャイルなど他の開発手法との違いもわかりやすく紹 […]
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.12.11
システム開発トラブルの原因と事例徹底解説!失敗回避と法的対応のポイント
システム開発におけるトラブルは、遅延や予算超過、仕様の齟齬、さらには運用段階での障害など多岐にわたります。本記事では、トラブル発生の原因から具体的な事例までをわかりやすく紹介するとともに、発注者や開発者が取 […]
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.12.02
システム開発を依頼するなら押さえたい!依頼書作成から費用・流れを解説
システム開発を外部に依頼する際、適切な準備と知識がなければコストや納期、品質で失敗するリスクが高まります。本記事では、依頼書の作成から全体の進行フロー、費用相場、開発手法の選び方、そして発注先の探し方まで、 […]
- #IT化推進
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.11.27
システム開発の相場を徹底解説|単価から費用管理・外注のポイントまで
システム開発の費用相場と単価の基礎知識 システム開発を外注する際、最も気になるのが費用の相場や内訳です。費用が不透明だと予算オーバーのリスクや開発の進行トラブルも招きやすくなります。本記事では、システム開発 […]
- #システム再構築
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.10.17
システム開発におけるV字モデルとは?概要やメリット、他のモデルについても解説
システム開発にはさまざまな工程や手法があり、その中でもV字モデルは多くの現場で活用されています。 効率的かつ品質の高い開発を目指す方にとって、どのような開発モデルを選ぶかは重要なポイントです。 […]
- #IT関連情報
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.09.25
生成AIが変えるシステム開発 ― 2025年の最新トレンドと活用法
近年、生成AIが急速に普及し、システム開発の現場でも大きな変化をもたらしています。 2025年以降は「生成AIを前提とした開発体制」が本格的に広がる転換点となる年と言えそうです。 本コラムでは、生成AIがどのようにシステ […]
- #AI関連情報
- #IT関連情報
- #デジタル化
- #業務効率化
- #生産性向上

2025.08.25
【2025年最新版】システム開発には補助金・助成金の活用を!
業務効率化や顧客満足度向上がカギとなっている今「新しくシステムを導入したい」「今のシステムを刷新してより生産性の向上に努めたい」という企業が多くなっています。しかしながら、システムの開発や再構築には多額の費用がかかるため […]
- #システム再構築
- #助成金・補助金
- #基幹システム・Webシステム開発
- #生産性向上

2025.07.25
ローコード・ノーコードでは解決できない、オーダーメイド開発という選択肢
DX(デジタルトランスフォーメーション)への関心が高まる中、ローコード・ノーコード開発ツールの普及が加速しています。 「現場主導でアプリが作れる」「開発コストや期間を削減できる」といった利点から、業種業態を問わずさまざま […]
- #DX(デジタルトランスフォーメーション)
- #IT化推進

2025.06.25
レガシーシステムはなぜなくならない?使い続けるリスクを解説
DXの最大の障害とされるのがレガシーシステムです。 企業がITシステムの導入に取り掛かったのは、今に始まったことではなく、中には1980年代ごろから導入しているケースもあります。そのような中で、最先端を進ん […]
- #DX(デジタルトランスフォーメーション)
- #IT化推進
- #システム再構築
- #基幹システム・Webシステム開発


