
システム開発におけるV字モデルとは?概要やメリット、他のモデルについても解説

システム開発にはさまざまな工程や手法があり、その中でもV字モデルは多くの現場で活用されています。
効率的かつ品質の高い開発を目指す方にとって、どのような開発モデルを選ぶかは重要なポイントです。
本記事では、V字モデルの概要や特徴、メリット・デメリット、他の開発モデルとの違いまで幅広く解説します。
V字モデルが注目される理由や、それぞれの工程がどのように連携しているのかも分かりやすくまとめていますので、
開発手法を学びたい方や、最適なプロジェクト運用を考えている方に役立つ内容です。
この記事を読むことで、V字モデルについての理解を深め、ご自身のシステム開発に活かせるヒントが見つかります。
◆システム開発のV字モデルとは?IPAの定義についても
システム開発のV字モデルは、IPA(情報処理推進機構)が示す開発プロセスの一つで、
要件定義から設計、実装、テスト、運用までの各工程がV字型に対応し、
それぞれの工程と同じ高さで対になる検証活動(レビュー・テスト)が位置付けられています。
開発が左から右へV字を描くように進み、左側で定義や設計活動、右側で検証活動が行われます。
このモデルでは、各工程ごとに成果物や目標を明確にし、その時点でレビューやテストを通じて品質を確保します。
たとえば、要求分析で求められるシステムの姿を明確にし、それに対する実装後の運用テストで、
実際に意図通り動くかを確認します。
IPAが示す定義(参照:IPA「ソフトウェア開発管理ガイドライン」45ページ)によれば、
V字型は「設計と検証/テスト工程を一対に対応させ、品質管理や管理項目を明確にする」ことが特徴です。
実際のプロジェクトでV字モデルを用いることで、各工程ごとに品質を担保しつつ、
工程間の対応関係を明確化できます。これにより、ミスや手戻りの発生リスクを抑え、
システムの信頼性や開発効率を高めることができます。
システム開発に必要な工程の見える化や、問題発生時の対応のしやすさもV字モデルの大きな強みです。
◆システム開発のV字モデルの要素ごとの対応
V字モデルでは、開発の各工程ごとにそれに対応するテストや検証工程が設定されています。
たとえば、要件分析では運用テスト、システム要件定義にはシステム適格性確認テスト、
ソフトウェア設計にはソフトウェアテストが並び、工程ごとに対応する検証項目が存在します。
これにより、各工程での成果物と品質基準が明確となり、問題の早期発見がしやすくなります。
要件分析と運用テスト
要件分析は、システム開発の出発点として、顧客やエンドユーザーが必要とする機能や性能を詳細に洗い出し、
明文化する工程です。ここで定義された要件は、プロジェクト全体の土台となり、
全ての設計・開発活動の指針となります。
一方、運用テストは開発の終盤で実施され、システムが現実の運用環境で適切に動作するかどうかを確認します。
運用テストでは、シナリオに沿った試験や現場での利用を想定し、実際の運用時に問題が発生しないか、
定義された要件通りに動くかを厳密に検証します。
要件分析と運用テストは、ちょうどV字モデルの左端と右端に位置し、
「何をつくるか」と「つくったものが本当に求められていたものか」を結びつける重要な対応関係です。
たとえば、ある業務システムの開発で「従業員の勤怠をリアルタイムに把握できる」という要件が
分析工程で明記されていれば、運用テストでも実際に様々な勤務形態に対応できているか、
管理者画面で適切に情報更新が反映されるかなど、現場に即した試験を行います。
最初に定義した要件を業務現場で本当に満たしているかどうか確かめることで、
ユーザーの満足度と業務効率の向上につながります。
システム要件定義とシステム適格性確認テスト
システム要件定義では、ユーザーや組織の業務要件をもとに、システムとして満たすべき機能や性能、
インターフェース、運用条件などを具体的に定めます。
ここで決まった内容が、システム開発における指標となり、
後続の設計や開発、テスト活動へ大きな影響を及ぼします。
システム適格性確認テストは、開発が完了したシステムが、
定義された要件をすべて満たしているかどうかを確認する工程です。
ここでは、システム要件定義書に記載された機能要件・非機能要件ごとに、
テスト計画とケースを用意し、漏れなくチェックします。
実際に入力データを変えて反応を見たり、異なる環境下での動作を検証することも必要です。
例えば、社内システムなら「月次レポート自動生成」「複数端末対応」
といった各要件に対応したテストが行われ、エラーの有無や性能をチェックします。
これにより、リリース前に要件との食い違いや見落としを減らすことができ、
システム導入後のトラブル抑制にもつながります。
要件とテスト内容が一対一で対応しているため、プロジェクト全体の品質保証を担保しやすくなります。
ソフトウェア設計とソフトウェアテスト
ソフトウェア設計では、システム要件を実現するための具体的な機能構成やデータの流れ、
モジュール構成、インターフェース設計などを詳細に決めていきます。
設計書を作成し、設計内容に基づき開発が進むため、この段階での品質が後続工程に大きく影響します。
ソフトウェアテストは、完成したソフトウェアが設計仕様通りに動作しているかを検証する工程です。
単体テストや統合テストなど複数のレベルで実施され、設計で定めた機能や入出力、
画面遷移などの動作確認をします。
テストケースは設計内容から抽出され、期待される動作との一致を厳密に評価します。
現実には、設計段階でのミスや設計漏れが後々大きなバグや不具合として現れることが多く、
テスト工程で早期発見することが重要です。
設計ドキュメントとテストケースの対比によって、設計精度と実装品質の両方を高めることができます。
この関係性により、システム全体の健全な品質管理が実現されます。
◆システム開発でV字モデルを採用するメリット
V字モデルを採用すると、プロジェクト工程が明確になり、各段階の品質管理が実施しやすくなります。
また、工程ごとにテストを実施するため問題の発見が早く、手戻りリスクを低減できます。
開発と検証が一体となることで、全体の進行管理やドキュメント整備もスムーズです。
品質を意識した開発ができる
V字モデルでは、各工程ごとに検証作業を組み合わせて進めるため、
開発工程のどの段階でも品質の確認が行われます。
設計の段階で仕様に沿った内容になっているか確認しながら進めるため、
後工程で問題が見つかるリスクを低減できます。
ソフトウェア開発では一度作業が先に進むと、その後の修正には大きなコストと工数がかかる場合が多いです。
しかしV字モデルを採用することで、工程ごとの成果物や設計書・仕様書といったドキュメントをもとに、
各段階で徹底的なレビューやテストが行われます。
この流れによって、手戻りの発生を早めに食い止めることができ、品質向上が自然と意識される開発となります。
たとえば、要件定義段階で作成したドキュメントが設計やテスト計画でも活用され、
定義内容のヌケ・モレに気づきやすくなるのも大きな効果です。
こうした仕組みにより、結果として顧客が期待する機能や性能を安定して提供でき、
運用後のトラブルも発生しにくくなります。
全体を通して品質担保の意識が高まり、長期的な運用や法改正などへの対応もしやすい基盤作りにつながります。
開発チームとテストチームの連携が図りやすい
V字モデルは開発工程ごとに対応するテスト工程がはっきりしているため、
開発担当者とテスト担当者との連携がスムーズに進みます。
たとえば、設計段階で決まった仕様をもとに早い段階からテスト計画を立てることができ、
開発チームとテストチーム双方向での情報共有が促されます。
現場では、通常開発工程が進むごとにテスト準備も進めていくため、
仕様変更や追加があった場合でも事前に双方に伝わりやすくなります。
また、成果物ごとにレビューを重ねる文化が定着することで、テスト観点から指摘が出たり、
逆に開発観点で指摘されるべき項目が明確になるため、チーム全体として一体感をもった開発が実現できます。
V字モデルは「設計とテストの一対一対応」を特徴としているため、
担当者間の意思疎通や協力が自然と生まれやすいです。
作業の属人化を防ぎ、お互いの作業意図を理解しながら進められるため、
最終的には品質向上にも大きく貢献します。
このように、チーム内の信頼関係やコミュニケーションを深める開発手法としても有効です。
プロジェクトのマネジメントがしやすい
V字モデルでは、各工程と成果物が明確に定義されているため、
プロジェクト全体の進捗や課題を把握しやすいです。
工程ごとに成果物の完成とレビューが区切りとなるため、進捗管理や品質管理のタイミングが明確になります。
実際に、計画を細かく立てやすくなり、各フェーズの完了判定やリスク抽出がタイムリーに行えます。
たとえば、設計工程に遅れが発生した場合でも、どの工程にどのくらい影響が出るかを予想しやすく、
対策も打ちやすいです。
また、ドキュメントが体系的に残るため、万が一担当者交代が必要な場合でも引継ぎが容易です。
さらに、工程間の対応関係が明確なので、変更管理や品質保証にも役立ちます。
たとえば、要求変更が生じた際には、どのテストや設計に影響するかをすぐに追跡でき、
再テスト計画にも反映しやすいです。
こうした仕組みがあることで、プロジェクト全体を見渡したマネジメントが可能となり、
遅延や品質低下といったリスクに早期対応できる体制が築けます。
具体的な管理指標や進捗レポートも複数の工程で作成できるため、経営層や顧客への説明も容易になります。
各工程ごとの成果物をドキュメントとして残しやすい
V字モデルでは、各工程ごとに成果物を明確にし、その都度ドキュメント化することが重視されます。
設計フェーズでは設計書、実装フェーズではプログラム一覧や仕様書、
テストフェーズではテスト項目や報告書など、段階ごとに必要な書類を体系立てて作成していきます。
この仕組みにより、プロジェクト全体の進行が可視化され、後からの見直しや監査対応も容易です。
たとえば、数年後システムの改修や保守が必要になった場合でも、
残されたドキュメントを活用して仕様の把握や変更履歴の確認ができます。
また、プロジェクトメンバーが変わった際にも、業務の引継ぎがスムーズにでき、
組織全体のノウハウ蓄積にもつながります。V字モデルは進捗管理だけでなく、
知識の伝達や属人化防止という観点でもメリットが大きいといえるでしょう。
体系的にドキュメント整備が進められ、長期的に運用しやすいシステムを実現できる点が特徴です。
◆システム開発でV字モデルを利用する際のデメリット
V字モデルを利用する際は、仕様変更が難しかったり、開発期間が長期化しやすいという課題があります。
また、顧客が成果物を実際に目にするタイミングが遅くなる傾向もあります。
柔軟な変更や素早いフィードバックが求められる場合には、運用面で工夫が必要です。
開発途中での仕様変更に対応しにくい
V字モデルは、各工程が厳密に区切られているため、
開発をスタートした後の仕様変更に柔軟に対応しにくい特徴があります。
最初の要件定義や設計段階で決まった内容を各工程で順に確認しながら進める仕組みのため、
進捗中に大きな変更が入ると、前の工程から見直しややり直しが発生します。
実際に、顧客から「業務フローの一部を追加したい」「新たなインターフェースを導入したい」
といった要望がプロジェクト途中で出される場面もありますが、
V字モデルでは関連する全ての設計書・テスト計画も修正対象となり、
スケジュールや予算の再調整が必要となる場合もあります。
変更を許容しにくいため、事前の要件定義や仕様策定段階で徹底的なヒアリングや関係者間の合意形成が必要です。
逆に、変更を繰り返してしまうと、進捗や品質に悪影響が出るリスクが高くなります。
一方で、開発期間の途中での柔軟な対応が求められる案件や、
業務要件が流動的になりやすいプロジェクトには工夫が必要となります。
開発期間が長期化しやすい
V字モデルの特徴である各工程の厳格な区切りやドキュメント作成は、品質担保に役立つ一方で、
工程ごとにレビューや承認を繰り返すため開発期間が長くなりやすい傾向にあります。
たとえば、要件定義・設計・実装・テストなど、それぞれの工程で成果物をまとめ、チェックし、
次工程に進むまでのプロセスに時間がかかります。
複数の関係者が関与する場合は、説明・調整のための会議やレビューも増え、
プロジェクト全体のタクトタイムが長くなります。
特に規模の大きなシステムや複雑な要件をもつ案件では、1工程の遅れが後工程に波及し、
期間がさらに延びるリスクもあります。
さらに、運用テストやシステム適格性確認テストなど最終段階の検証作業も省略できないため、
開発終盤に多くのリソースを投入する必要が生じ、予想外の遅延につながることもあります。
スケジュール管理を徹底し、効率的に各工程を推進するための体制整備と進捗共有が重要です。
顧客に成果物を見せてレビューするまでの期間が遅くなることがある
V字モデルでは、各開発工程ごとに設計やテスト活動を重ね、
最終成果物ができあがるまでプロトタイプや実動作を顧客が確認できない場合があります。
そのため、顧客がイメージする機能や操作性と完成品にギャップが出るリスクがあります。
とくに画面設計や業務フローの部分など、顧客の業務に密着する部分では、
紙や仕様書だけでは伝わらないニュアンスが多く、実際の成果物を手にするまでフィードバックが遅れがちです。
その結果、納品後に「動作イメージが異なる」「思ったより使い勝手が悪い」
といった問題が明らかになることも珍しくありません。
こうしたリスクを回避するためには、途中途中でモックアップや画面サンプル提示、
小単位での確認会や中間レビューを実施するのが効果的です。
顧客と開発チームが頻繁にコミュニケーションできる工夫をすることで、
最終成果物を顧客が納得して受け入れる確率を高める必要があります。
◆V字モデルでシステム開発を行う時のポイント
V字モデルを成功に導くには、要件定義の精度を高め、
定期的なレビューや他の開発手法との組み合わせを検討することが重要です。
事前準備や合意形成を徹底しつつ、柔軟な対応やチーム間の連携も重視すると良いでしょう。
要件定義の精度を徹底的に高める
V字モデルでは、初期の要件定義が全体の設計やテスト計画の基盤となるため、
精度の高い要件定義が極めて重要です。要件に曖昧さや抜け・漏れがあると、
後続の設計・開発・テスト全てに影響が及び、手戻りやトラブルの原因になります。
顧客や業務担当者との十分なヒアリング、現状の業務理解、業界特有の要件の洗い出しを徹底的に行い、
ドキュメント化・合意形成を経て次の段階へ進むべきです。
この過程で、実現困難な機能や要件間の矛盾なども発見しやすくなり、
後から品質問題や手戻りが生じるリスクを削減できます。
また、各要件に優先度を設定し、重要度が高いものから着実に詳細化していくことで、
プロジェクト全体の推進力を高める効果も生まれます。
発注側・受注側の双方で検討し、合意を得た内容をもとに全体を進めていく姿勢が大切です。
要件定義段階でリスクや課題をできる限り可視化し、議論・調整を重ねることが、
品質・納期ともに優れたプロジェクト推進につながります。
定期的に質の高いレビューを実施する
V字モデルの強みを活かすためには、工程ごとに質の高いレビューを欠かさず実施することが重要です。
要件定義や設計、実装、テスト各フェーズごとの成果物に対し、
関係者による複眼的なチェックを取り入れることで、
独りよがりの設計や想定外の抜け・漏れを早期に発見できます。
定期的なレビューは設計ミスや誤解を未然に防げるだけでなく、
プロジェクトメンバー間の知識共有や技術力の底上げにも有効です。
特に、テスト仕様書や設計書の段階で具体的な動作確認を想定したレビューを行うことで、
後の工程での手戻りを大幅に減らす効果があります。
たとえば、レビューを定例化し、第三者(他チームやQA担当者)が参加する仕組みを取り入れると、
より客観的な視点で改善点を発見しやすくなります。
また、顧客や利用者も巻き込んだプロトタイピングや中間成果物の確認も効果的です。
プロジェクトの品質を高く維持し続けるための重要なポイントとなります。
他の開発モデルとのハイブリッドを検討する
V字モデルは品質管理やドキュメント重視に適していますが、
柔軟性や迅速なフィードバックにはやや不向きな面もあります。
そのため、規模や目的、状況に応じてアジャイルやプロトタイピング手法と組み合わせる
「ハイブリッド型」の採用を検討するのも効果的です。
たとえば、要件定義や設計のフェーズはV字モデルを基本としつつ、
実装やテストフェーズだけ小規模なイテレーションやアジャイル要素を取り入れる方法があります。
これにより、全体の品質やドキュメント管理は維持しながら、
部分的にフィードバックサイクルの短縮や顧客とのコミュニケーション強化を図ることができます。
また、画面設計やユーザー体験に関する部分は早い段階でプロトタイプやモックアップを作成し、
顧客に実物を見せながら仕様を確定していくやり方も有効です。
自社や顧客の文化、プロジェクト特性に応じて柔軟に手法をミックスすることで、
失敗リスクを抑えつつ最適な開発体制を構築できます。
◆V字モデル以外のシステム開発モデルの例
V字モデル以外にも、ウォーターフォールモデル、スパイラルモデル、アジャイルモデル、W字モデルなど、
多様な開発手法があります。
プロジェクトの規模や目的、組織の特性に応じて使い分けることで、開発効率や品質向上に役立ちます。
ウォーターフォールモデル
ウォーターフォールモデルは、システム開発において伝統的かつ最も基本的な手法の一つです。
要件定義から設計、実装、テスト、運用までの工程を順番に上から下へと進め、
それぞれの工程が完了してから次の段階へ移行します。
工程ごとに明確な区切りがあり、進捗管理や品質確認がしやすい点がメリットです。
特に、大型プロジェクトや仕様変更が少ない案件に適しています。
要件や設計が初期段階でしっかり固まっている場合、計画通り進めやすく、
関係者間の合意形成も容易です。ドキュメント重視でプロジェクト管理がしやすいため、
官公庁や大手企業の業務システムで多く採用されています。
しかし、一度進んだ工程に手戻りしにくいため、開発中の仕様変更には対応しにくいというデメリットもあります。
ユーザーの要望や市場環境が変化しやすいプロジェクトや、早い段階で成果物のフィードバックが必要な場合は、
他の手法の検討も必要です。
開発全体を段階的・計画的に進めるのがウォーターフォールモデルの特徴です。
スパイラルモデル
スパイラルモデルは、システム開発を複数のサイクル(スパイラル)に分けて繰り返し進める手法で、
計画・設計・実装・評価を何度も反復しながら徐々にシステムを完成させていきます。
最初に全体像を決めるのではなく、小さな機能やサブシステムごとに計画・開発・評価・改善を繰り返します。
このモデルの利点は、各サイクルごとにリスク分析やユーザー評価ができ、
要求の変化やリスクの高い部分を早期に発見・解決しやすい点です。
ユーザーのフィードバックを反映しやすく、品質やユーザー満足度の向上につながります。
また、段階的なリリースやデモンストレーションができ、
顧客と開発チームのコミュニケーションも密に取れます。
大規模なプロジェクトや要件の不確実性が高い場合に向いている手法です。
ただし、繰り返し開発に伴うコストやスケジュール管理の複雑さ、進行管理の難しさもあるため、
管理手法や体制整備が求められます。
アジャイルモデル
アジャイルモデルは、従来の重厚長大な開発手法とは異なり、
小さなサイクル(イテレーション)を繰り返しながら、変化に柔軟に対応できる開発手法です。
短い期間ごとに設計・実装・テストを行い、段階的にシステムを成長させていきます。
顧客やエンドユーザーとのコミュニケーションを重視し、要件の変更にも迅速に対応できるのが特長です。
スクラムやカンバン、XP(エクストリームプログラミング)などさまざまなフレームワークが存在し、
エンジニアや顧客が協力して作業を進めるチーム開発に向いています。
製品イメージを実際に動かしながら確認できるため、要件の誤解や完成品イメージのズレを最小限に抑えられます。
Webサービスやスタートアップなど、スピード感ある開発が求められる分野で多く採用されています。
工程の重複や設計の複雑化が起きやすい点には注意し、適切な運用とチーム力が重要です。
W字モデル
W字モデルは、V字モデルの要素に加え、工程ごとにテストや検証作業をさらに細分化し、
各段階で問題を早期発見・修正できるようにした進化型の手法です。
Wの左半分で要件・設計・製造など各工程を行い、右半分で単体テストや結合テスト、
システムテストまで細かく実施します。
このモデルの特徴は、製造前に設計内容のテストも組み込む「早期テストの実施」にあります。
それにより不具合の早期検出ができ、下流工程での手戻りやコスト増を削減しやすくなります。
設計作業ごとに「設計の妥当性確認テスト」や「設計書レビュー」を行う仕組みが組み込まれているため、
品質を段階的に確保できるのが強みです。
たとえば、大規模システムの開発やミッションクリティカルな分野で、
プロジェクト全体の品質担保やリスク低減のために活用されます。
一方、細かなテストや検証を重ねるため、リソースや開発期間が増加する傾向もあります。
システム品質に特にこだわる開発で、V字モデルよりさらにきめ細かい管理が求められる場合に適しています。
◆まとめ:システム開発におけるV字モデルを理解しよう
V字モデルは、各工程ごとに設計と検証工程が対応し、品質管理や進捗把握を明確にできる手法です。
全体を通じてドキュメント管理やチームの連携も図りやすく、安定したシステム開発・運用ができるのが特徴です。
一方で、柔軟な変更や迅速な対応には課題もあるため、
プロジェクト特性に応じて他の手法や工夫と組み合わせることが重要です。
開発における基本を押さえつつ、状況に合わせ最適な方法を選択することが求められます。
V字モデルの特徴や活用ポイントを理解し、システム開発現場で効果的に活用してみてください。
もし自社プロジェクトへの導入や運用方法についてさらに詳しく知りたい場合は、
専門家へ相談してみるのもおすすめです。
「システム開発におけるV字モデルとは?概要やメリット、他のモデルについても解説」に関連する記事

2026.01.15
システム開発における基本設計とは?進め方から成果物まで解説
システム開発の基本設計は、要件定義から詳細設計へと進む重要な工程です。本記事では、初心者から中級者向けに基本設計の役割や進め方、特徴的な設計書の種類や作成のポイントをわかりやすく解説します。 […]
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発
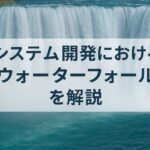
2025.12.23
システム開発におけるウォーターフォールを解説:工程ごとの特徴と他手法との比較も
ウォーターフォール開発は、システム開発の中でも伝統的で多くの大型プロジェクトに採用されてきた手法です。本記事では、ウォーターフォールの各工程を詳しく解説し、アジャイルなど他の開発手法との違いもわかりやすく紹 […]
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.12.11
システム開発トラブルの原因と事例徹底解説!失敗回避と法的対応のポイント
システム開発におけるトラブルは、遅延や予算超過、仕様の齟齬、さらには運用段階での障害など多岐にわたります。本記事では、トラブル発生の原因から具体的な事例までをわかりやすく紹介するとともに、発注者や開発者が取 […]
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.12.02
システム開発を依頼するなら押さえたい!依頼書作成から費用・流れを解説
システム開発を外部に依頼する際、適切な準備と知識がなければコストや納期、品質で失敗するリスクが高まります。本記事では、依頼書の作成から全体の進行フロー、費用相場、開発手法の選び方、そして発注先の探し方まで、 […]
- #IT化推進
- #システム開発工程
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.11.27
システム開発の相場を徹底解説|単価から費用管理・外注のポイントまで
システム開発の費用相場と単価の基礎知識 システム開発を外注する際、最も気になるのが費用の相場や内訳です。費用が不透明だと予算オーバーのリスクや開発の進行トラブルも招きやすくなります。本記事では、システム開発 […]
- #システム再構築
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.09.25
生成AIが変えるシステム開発 ― 2025年の最新トレンドと活用法
近年、生成AIが急速に普及し、システム開発の現場でも大きな変化をもたらしています。 2025年以降は「生成AIを前提とした開発体制」が本格的に広がる転換点となる年と言えそうです。 本コラムでは、生成AIがどのようにシステ […]
- #AI関連情報
- #IT関連情報
- #デジタル化
- #業務効率化
- #生産性向上

2025.08.25
【2025年最新版】システム開発には補助金・助成金の活用を!
業務効率化や顧客満足度向上がカギとなっている今「新しくシステムを導入したい」「今のシステムを刷新してより生産性の向上に努めたい」という企業が多くなっています。しかしながら、システムの開発や再構築には多額の費用がかかるため […]
- #システム再構築
- #助成金・補助金
- #基幹システム・Webシステム開発
- #生産性向上

2025.06.25
レガシーシステムはなぜなくならない?使い続けるリスクを解説
DXの最大の障害とされるのがレガシーシステムです。 企業がITシステムの導入に取り掛かったのは、今に始まったことではなく、中には1980年代ごろから導入しているケースもあります。そのような中で、最先端を進ん […]
- #DX(デジタルトランスフォーメーション)
- #IT化推進
- #システム再構築
- #基幹システム・Webシステム開発

2025.05.21
突然の“保守打ち切り”がもたらすリスクと、備えるべき選択肢
近年、開発会社の倒産やエンジニアの流出により、システムの保守が継続できなくなるケースが相次いでいます。 特に、企業の業務を支える基幹システムが「孤児化」する事態は、業務継続に深刻な影響を及ぼします。 本コラムでは、システ […]
- #システム保守
- #基幹システム・Webシステム開発
- #業務効率化
- #生産性向上

2025.04.25
システム開発の要件定義、発注側がすべきこととは?
システム開発は開発会社にすべて任せればいい、というわけではありません。経験が豊富なプロであっても発注側の意見や要望がなければ良いシステムを作ることは難しいでしょう。そこで大切となってくるのが「要件定義」です。要件定義では […]
- #システム保守
- #システム再構築
- #システム開発工程



